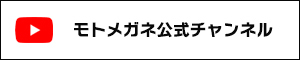近年電動キックボードの普及が進み、都市部を中心に日常の移動手段として利用されることが増えてきました。しかし、電動キックボードの利用時の交通ルールを正しく理解しておらず、違反とみなされている事例も多数見られます。
そこで今回は、電動キックボードの特徴や適用される交通ルールについて詳しく紹介します。
電動キックボードはどのような乗り物?
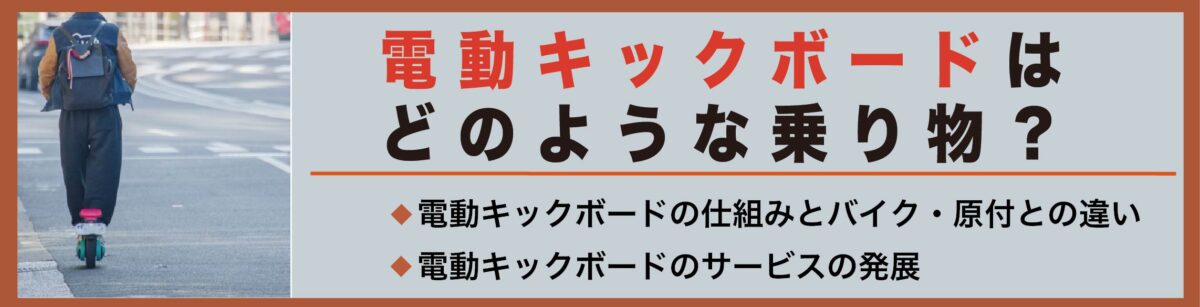
電動キックボードは、コンパクトなデザインと手軽な操作性から近年利用者が増えており、レンタルサービスの展開地域も拡大されています。
しかし、電動キックボードはバイクや原付とは異なる仕組みを持っているため、それらとは異なる感覚で利用しなければなりません。
電動キックボードの仕組みとバイク・原付との違い
そもそも電動キックボードは、バッテリーとモーターを搭載した二輪車であり、基本的にはキックで加速しつつ、モーターの力で走行する乗り物です。電動キックボードには、主に「特定小型原動機付自転車」と「原動機付自転車(原付)」扱いとなるモデルの2種類があります。
特定小型原動機付自転車に該当するモデルは最高速度が20km/h以下であり、一定の基準を満たしていれば、16歳以上は免許不要で利用できます。
一方で、最高速度が20km/hを超えるもの等は原付として扱われ、運転には免許が必要です。電動キックボードとバイクや原付と大きく違う点として、交通ルールの違いが挙げられます。
特定小型原動機付自転車として登録された電動キックボードは、歩道を走行できるモデル(最高速度6km/h以下)も存在するように、交通環境に応じて利用可能です。また、バイクや原付は車道走行が基本ですが、電動キックボードは自転車レーンを走行できる場合もあります。
なお、バイクや原付と異なりヘルメットの着用は努力義務ですが、ヘルメット非着用時の致死率の高さを考慮して、着用することが推奨されています。
電動キックボードのサービスの発展
日本では電動キックボードに関する法規制が厳しく導入が遅れていましたが、近年の交通法規の改正によりレンタルサービスの規模が拡大しています。
利用時には専用アプリを通じて最寄りのキックボードを探し、QRコードをスキャンして利用開始でき、目的地に到着した後は指定の駐車エリアに返却する流れとなっています。
バイクや原付に比べて維持費がかからず、駐車スペースを確保しやすい点が、利用者が増えている要因のひとつでしょう。
しかし普及が進む一方で、安全性やルールの順守が課題となっています。
特に歩行者との接触事故や、ルールを守らず車道を逆走するケースが問題視されており、今後はより厳格なルール作りが求められそうです。
また、レンタルサービスを利用する際は利用者自身が利用規約を理解し、適切な場所での返却や、安全運転を心掛けることが重要なポイント。今後はバイクや原付とのすみ分けが明確になり、より安全に利用できる環境が整っていくことが予想されます。
電動キックボードにはどんな交通ルールがある?
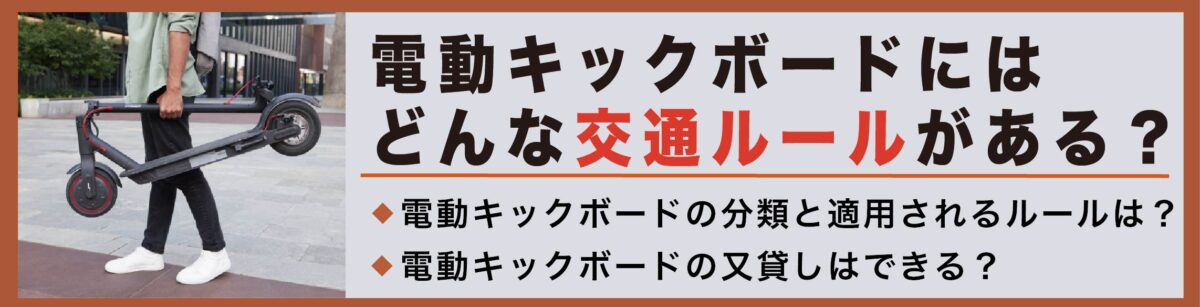
電動キックボードの分類と適用されるルールは?
電動キックボードは、最高速度が20km/h以下であり一定の基準を満たしている場合のみ、公道の一番左側の車両通行帯を走行することが可能です。 ただし、夜間走行時には前照灯を点灯させることが義務付けられており、また最高速度表示灯を点滅させなければなりません。
また原付に該当するモデルの場合は運転免許が必要となり、ヘルメットの着用も義務付けられています。
また、電動キックボードにおいても飲酒運転は厳しく禁止されており、飲酒した状態で運転すると道路交通法違反となり、処罰が科されることになります。
市街地をスマートフォンを注視したり、イヤホンを装着したりしながら走行するユーザーも見られますが、このような「ながら運転」もNG行為です。
電動キックボードの又貸しはできる?
電動キックボードをレンタルした場合、「他人に貸して使用させることができるのか」という疑問を持つ人もいるかもしれません。
一般的に電動キックボードのレンタルサービスでは、「契約者本人のみが利用できる」という規約が設定されている場合が多数を占めます。
レンタル契約の際は契約者の情報が登録されるため、それ以外の人が運転すると契約違反となる可能性も。 加えて、二人乗り運転も禁止されているため、こういった行為は絶対に避けましょう。
また、万が一又貸しした相手が事故を起こした場合、契約者本人が責任を問われることがあるため注意が必要です。
ちなみにレンタル契約には、保険や補償の適用条件が定められており、契約者本人が利用している場合に限り、事故時の補償が適用されるケースが一般的です。
契約者以外が無断で運転した場合は保険の適用外となる可能性が高く、事故の際には損害賠償を求められることも予想されます。
まとめ
電動キックボードは、おおまかに2種類に区分され、それぞれ速度制限や通行場所に大きな違いが見られます。
いかなる場合であっても又貸しは避け、加えて16歳に満たない人に利用を推奨するのは避けましょう特に、法整備が進行中の現時点では、歩行者と車両の双方に注意して走行することを心がけたいものです。