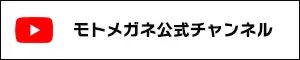電動バイクには、ガソリンを使用せずにバッテリーで走行するため給油の手間がなく、維持費が抑えやすいという特徴があります。
徐々にユーザーが増加している電動バイクがどのような乗り物なのか、バッテリーの特徴や実際にトラブルが発生した際の対処法、走行時の工夫などに注目して詳しく見ていきましょう。
バッテリーの特徴とトラブル時の対処法

上述のように、電動バイクはエンジンオイルの交換が不要かつ排気ガスを出さないことから、環境に配慮したエコ・モビリティとして注目されています。
一方で、ガソリンバイクと比べると航続距離が短い傾向があり、長距離走行には向いていないと指摘するユーザーも少なくありません。
そのため電動バイクは、近距離の通学や買い出しといった日常使いに適した乗り物と言えるでしょう。
特に、都市部ではバッテリーや充電器のシェアリングサービスが普及しつつあります。
バッテリーの種類と特徴は?
しかし、電動バイクにはバッテリーに関する特有の管理方法や、車体の保管に関する注意点もあります。
電動バイクの最大の特徴は、バッテリーを動力源としている点。バッテリーには「内蔵型」と「取り外し型」の2種類があり、それぞれ異なる特性があります。
まず、内蔵型バッテリーは車体に組み込まれたタイプのバッテリーで、基本的に取り外しができません。
このタイプのメリットは、あまりバッテリースペースの開閉を想定していないため車体設計の自由度が高く、バイクの重量配分が最適化されやすい点にあります。
一方で、充電する際にはバイクごと電源のある場所まで移動しなければならないため、外出時は充電設備の確保が課題となります。
そして取り外し型バッテリーは、バイクから簡単に取り外して室内でも充電ができるタイプ。
家庭用コンセントで充電できるモデルも多く、予備バッテリーとの交換も容易であるといったように、利便性が高いのが特徴です。
ただし、バッテリーを持ち運ぶ必要があるため、重量があるものを取り扱う際は慎重になる必要があります。
なお、バッテリーは気温の影響を受けやすく、特に寒冷地ではバッテリー内部の温度低下によって航続距離が短くなる傾向にあるのも重要なポイント。
これは、低温環境下ではバッテリー内部の化学反応が鈍くなり、放電効率が下がるためです。
そのため冬場に電動バイクを使用する場合は、直前まで室内で保管するといった、バッテリーを適切に保温する工夫が求められます。
走行中にバッテリーが切れた場合は?
では、走行中にバッテリーが切れた場合はどうなるのでしょうか。
電動バイクの場合、ガソリンバイクのような「予備燃料」がないため、バッテリーが完全に放電すると走行不能になります。
万が一、公道でバッテリーが切れてしまった場合は、バイクを降り、迅速に対応しましょう。
これは、電欠もガス欠の場合と同じように道路交通法違反となるケースがあるためです。
最終的に取り締まるかどうかは現場の判断になりますが、事故のリスクがあるにもかかわらず対応策を講じなかったということで取り締まられる可能性があります。
法律上、電動バイクも原動機付自転車と同様に扱われるため、バッテリー切れで公道を押して歩くこと自体は違反にはなりません。
周囲に受電機器が設置されている施設がないかを確認し、注意しながら歩いて向かいましょう。
しかし、ドライバーが歩くスペースが確保できないといった場合に危険が伴うため、走行中もできるだけバッテリー残量を把握しながら走行すべきであることを念頭におきましょう。
なお、回線の不良といったことが原因で、灯火が適切に機能していない場合に関しても違反となることがあります。
他にも、電動バイクのバッテリーは寿命があるため、長年使用していると最大航続距離が短くなる場合があります。
接触不良や速度の低下が感じられた時は、早期の交換が求められます。
車体の保護と省エネ運転

ガソリンバイクと電動バイクでは構造が異なりますが、車体の保護や省エネ運転に関する基本的な考え方は共通しています。
バイクの寿命を伸ばすための保管方法
電動バイクは防水性能を備えたモデルが多いものの、長時間雨にさらされることにより、配線や接続部分に水分が入り込むと電気系統の故障を引き起こす可能性があります。
また、バッテリー本体が水に濡れると、当然故障や劣化の原因となるため、できるだけ屋内やカバーをかけた状態で保管することが望ましいです。
梅雨など特に雨天となりやすい時期は、雨ざらしでの駐車やバッテリーの屋外での管理には特に注意したいところです。
バッテリー消費を抑える運転方法
また、電動バイクは省エネ運転を意識することで、航続距離を伸ばしやすくなります。
たとえば、急加速や急ブレーキを避け、緩やかなスロットルコントロールでの加速や一定速度で走行することで、バッテリーの消耗を抑えることができます。また、下り坂では回生ブレーキを活用することで、バッテリーの消費を抑えながらの走行も可能です。
さらに、タイヤの空気圧を適正に保つことも、電動バイクの燃費(電費)向上に役立ちます。
エンジンバイクの足回りと同様に、タイヤの空気圧が不足していると抵抗が増えてバッテリー消費が増えるため、定期的なチェックが推奨されます。
電動バイクは、メンテナンスの基本においてガソリンバイクと共通している部分も多く、日常的な点検や適切な保管を心がけることで、安全かつ快適に乗り続けることができます。
まとめ
電動バイクはガソリンバイクとは異なる特性をもち、バッテリーの管理や充電方法、気温による影響といった、独自の注意点がある乗り物です。
電動バイクのバッテリーを長持ちさせて航続距離を伸ばすためには、バッテリーの状態をこまめにチェックし、できる限りの省エネ運転を心がけることが望ましいでしょう。
今後も、技術の進化によって利用人口はさらに増えると考えられます。